サッカー日本代表 激闘日誌BACK NUMBER
<ドキュメント第1回キリンカップ>
「JAPAN CUP 1978」の衝撃 【後篇】
text by

加部究Kiwamu Kabe
photograph byPHOTO KISHIMOTO
posted2018/05/28 10:00
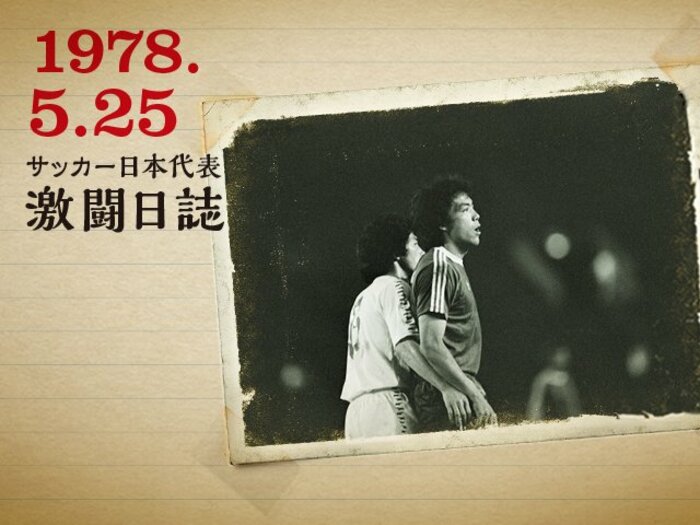
奥寺康彦がドイツで実感したもの。
日本人プロ1号の奥寺康彦は、夢のようなルーキーシーズンを送ることになった。ブンデスリーガ終盤の3試合で4ゴールを集中し、1FCケルンの14シーズンぶりの優勝に貢献。さらにドイツカップ決勝でも、デュッセルドルフを下し二冠を達成した。街をパレードし、市庁舎で溢れかえる市民と喜びをともにしながら、奥寺は改めて実感した。
「オレは街中の人たちの大きな期待を背負い、みんなの代表として戦っているんだ」
クラブ史上最良のシーズンを終えると、チームからはプレイメーカーのハインツ・フローエ、得点源のディーター・ミューラーら5人の主力がアルゼンチンワールドカップへ向けての代表合宿に招集され、残ったメンバーにアマチュア組を加えた18人の選手たちが日本行きの飛行機に乗る。羽田空港が近づくと、チームメイトが次々に奥寺に声をかけてきた。
「オクがいるから、このメンバーでも下手な試合はできないよな」「さあ、降りたらオクが主役だぞ」
大会の目玉として凱旋帰国した奥寺は、さっそく空港で報道陣に囲まれフラッシュを浴びる。そのまま東京プリンスホテルへ移動すると、バイスバイラー監督、レアー主将とともに記者会見に出席した。
「ドイツへ行ってサッカーが3倍楽しくなった。周りの選手のレベルが高いので、走ればいいパスを出してくれて、楽に扱える。今度はケルンのメンバーとして日本代表とも戦うが、負けないようにいいプレーを見せたい」
多くの子どもたちに本場のサッカーを。
開催概要が固まると、中野は地方への挨拶回りに明け暮れた。それまで日本代表の強化試合と言えば、単独チームを招いて数試合を重ねるか、3カ国対抗形式までだった。それが初のジャパンカップでは、8チームが全国10会場に分散して優勝を争うのである。
「積極的に手を挙げたのは神戸くらいで、外国同士の試合を引き受けてくれる県協会は少なかった。でも、とにかくできるだけ多くの子どもたちに本場の素晴らしいサッカーを見て欲しかったんです。チケット販売を各県協会に託し、一応目標の売り上げは設定しましたが、どれだけ招待券を配るかは裁量に任せました。あくまで地方に負担をかけるな、というのが日本協会の姿勢でしたから、赤字が出れば中央で被るしかありませんでした」
大会名は「ジャパンカップ1978」。あえて「第1回」と付けなかったところに、関係者の期待と不安が凝縮されていた。今後も続けて行きたいという願望はあったが、「せめてトントンにしないと続かないぞ」という危惧も同居していた。大会終了後に総括してみなければ、次があるとは公言できない辛い状況を表わしていたわけだ。
5月21日、奥寺は開幕戦を、慣れ親しんだ自分の庭のような三ツ沢球技場で迎えた。中学時代に何度も試合をしたスタジアムで、目の前には7年半勤めた古河電工の寮があった。だが「無我夢中で」戦い抜いたシーズンを終え、そのうえ帰国して時の人として注目を集めたこともあり、自分でも気づかぬうちに疲労が蓄積していたのだろう。
早朝6時からテレビの収録が続き、見かねたバイスバイラー監督がストップをかけたほどで、開幕の数日前から腹をこわしていた。それでもケルンとタイ代表では力の差が歴然としており、奥寺自身も何度かのチャンスを逸した後、ようやく得意の左足でゴールを決める。バイスバイラー監督は「きょうのオクは、体の調子が悪く、いつものようなプレーができなかった」と話したが、ドイツでは頭と右でしか決めていなかった奥寺は、「やっと左で決められた」と会見で笑みを湛えた。
