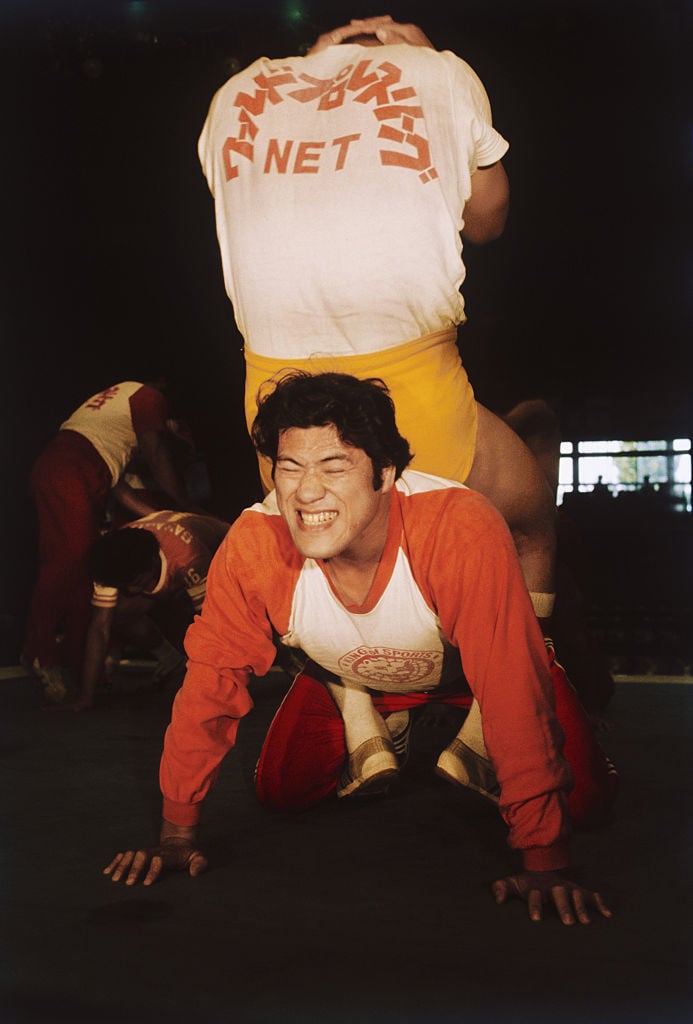熱狂とカオス!魅惑の南米直送便BACK NUMBER
「猪木寛至17歳」が力道山に出会った瞬間、“奴隷同然”な過酷労働…ブラジルで発掘した新聞と証言で知る「アントニオ猪木になるまで」
text by

沢田啓明Hiroaki Sawada
photograph byHiroaki Sawada
posted2022/10/24 17:04

来伯した力道山と猪木が会ったことを伝える当時の「サンパウロ新聞」
1957年初め、拓大空手部出身の三男・寿一がブラジル移住のパンフレットを見て強く魅かれた。「俺はブラジルへ行って一旗揚げたい」と家族に伝えたところ、すでに77歳だった母方の祖父・寿郎、母・文子、次女・久江とその夫、寛至を含む5男2女の総勢11人がブラジルへ渡ることになった。
当時、寛至は14歳。一家を挙げてブラジルへ渡る以上、行かないという選択肢はなかった。しかし、「外国へ行ってしまったら、日本でプロレスラーになれないのではないか」とも危惧した。
ひどい船酔いをして、何か食べても吐いてばかり
日本人のブラジル移住は、1908年に始まった。政府の支援を受けた会社が移住者を募集し、主として地方の農家の次男や三男が移民船に乗り込んだ。
ADVERTISEMENT
ただし、彼らの大半は数年だけ働いて金を貯めたら故郷へ錦を飾るつもりで、「移住」という認識はなかった。ところが、現実は移民会社の宣伝文句とかけ離れており、悲惨な生活を強いられるだけで金は貯まらない。多くの者が二度と日本の土を踏むことが叶わず、望郷の念に駆られながら現地に骨を埋めた。つまり、結果的に「移住者」となったのである。
第二次世界大戦が勃発して移民事業は中断されたが、戦後の1952年に再開された。
1957年2月初め、猪木家の人々を乗せた「さんとす丸」が横浜港を出発した。
猪木家と同じ「さんとす丸」でブラジルへ渡り、なおかつ同じ農場で働いた片山芳郎さんが、当時(片山さんは17歳)の記憶をたどってくれた。
「それまで見たことがなかったような大きな船で、ブラジルへの移住者約100家族、数百人が乗っていた。広い三等船室に、二段になった仮設ベッドがズラリと並んでいた。寝心地はあまり良くなかったな。
最初の頃はひどい船酔いをして、何か食べても吐いてばかり。一週間くらいしてやっと慣れ、普通に食事ができるようになった。でも、食事もおいしくはなかった」
出航から1カ月後に起きた悲劇
横浜港を出てから約1カ月後、船はパナマ運河に差しかかる。
船が停泊し、乗船者たちは下船してパナマ・シティーを散策した。当時、日本では貴重品だったバナナを安い値段で売っており、猪木家の一家はまだ青いバナナを食べた。
このことが、悲劇を招いた。子供たちは問題なかったが、長旅で疲れ気味だった高齢の寿郎が腸閉塞を起こし、パナマを通過後、息を引き取ったのである。
猪木の4歳年下で、一緒にブラジルへ渡った妹・佳子さんはこう語る。
「祖父は気宇壮大な豪傑タイプの人で、寛至兄さんのことを『この子はきっと大物になる』と言ってとても可愛がっていた。寛至兄さんも、非常に懐いていた。その祖父が旅の途中で亡くなってしまい、兄はとても悲しんでいました」
横浜港を出てから約1カ月半後、船はサントス港に到着した。列車に乗って山を越え、サンパウロの中央駅へ到着。猪木家と片山家の人々は、そこからサンパウロ州の奥地へ向かう列車に乗った。