Number ExBACK NUMBER
名作ノンフィクション 「江夏の21球」はこうして生まれた 【連載第3回】
text by

岡崎満義Mitsuyoshi Okazaki
posted2009/04/03 09:00
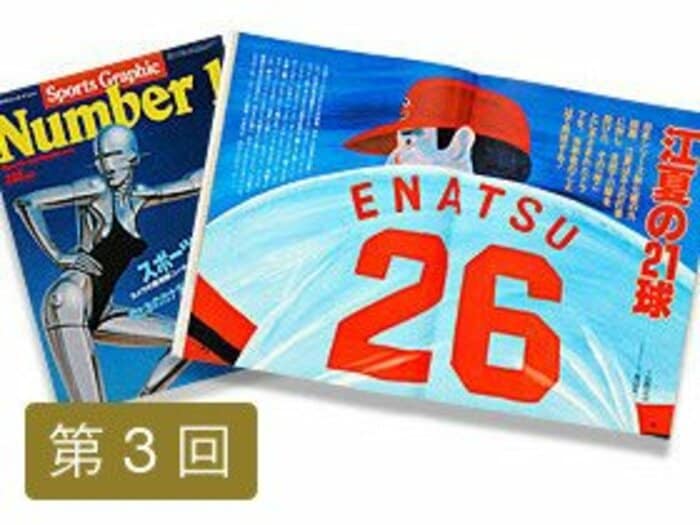
最終戦の前夜、江夏は寝ていなかった
「江夏の21球」は予想以上にうまく取材できた。スポーツ選手の取材で、これほどしっかり核心をつく取材ができた、というより、取材対象の人間が、これほど正直に、しかも微に入り細をうがつように話してくれることは、滅多にあることではなかった。たぶん江夏は、21球について話したくて仕方なかったのである。自分が体験した火傷(やけど)しそうな灼熱の時間、江夏の劇を誰かに発見してもらいたかったのである。だからこそ、これだけ心を開いて己を語ったのだ。
本稿のために新しくした取材でも、話はいつしか「江夏の21球」になっていた。
ADVERTISEMENT
「あのゲームを経験して、もう一歩泥沼に入りこんでしまったという感じやね。あれは単なる偶然、ラッキーでできたものじゃない。自分の頭と腕で『最高にやったぞ!』という試合やったからね。人からもあんな絶体絶命のピンチを抑えたんだから、どんな場面でも江夏なら抑えてくれるという大きな期待をかけられる。もちろん、それが大きな励みになったんやけど、その反面、重荷になって苦しかったな。偶然であんなことができたのだったら、重荷にもならなかった。これ、やった者にしかわからんやろうね。あれ以後、野球という底なしの泥沼に、ズブズブ入って身動きならなくなったもんね」
いわば“禁断の木の実”を食べた者だけが知る愉悦と苦しみ、というふうなものであろうか。
実はあの日、54年11月4日、江夏はほとんど寝ていなかった。前夜、親友の衣笠と二人で京都へ繰り出し、ドンチャン騒ぎをして朝帰りしていたのだ。大阪では顔を知られていて、人目がうるさい。タクシーを飛ばして京都へ行って羽を伸ばした。朝方、大阪のホテルへ帰り一時間ほどウトウトすると、もう球場入りの時間である。赤い目をして球場に行って軽い練習のあと、試合の始まる少し前から丹念なマッサージを三、四〇分受けた。貴重な睡眠の場でもあった。試合が序盤の3回に入ると、江夏はやおら起きて煙草を一服吸い、トイレへ入ってスッキリする。試合の経過は刻々と江夏に伝えられてくるが、ほとんど上の空で聞き流している。まだ江夏の「野球の時間」ではない。アンダーシャツを着がえて5回からベンチへ。この瞬間から江夏の頭と体は鋭く野球に反応しはじめる。相手チームの打者も味方チームの打者も区別をつけず、ボックスに入る打者を一人一人細かく観察する。観察というより、飢えた狼が牙を剥き、鋭い嗅覚で獲物を嗅(か)ぎまわっているようなものだ。この打者は今日はよくバットが振れているが、膝(ひざ)元で勝負できそうだ。……一人一人に対して頭の中で配球を考え幻のボールを投げてみる。これが江夏にとって最も大切な登板直前の「イメージ・トレーニング」なのだ。グラウンドで繰りひろげられている現実の試合と、江夏の頭の中でつくられていくもう一つの試合と、いわば「外」と「内」の二つのゲームが、しだいに江夏の体を万力(まんりき)のようにしめつけ、熱くしていく。マウンドへ登る高揚した気持ちが生まれてくる。
ベンチへ入った江夏はボールを左手からはなさない。入団三年目に肩をこわし、つづいて肘(ひじ)をこわし、血行障害もでた。少々の痛さは我慢できても、腕のしびれや感覚のなさはどうにもならない。左手にもった箸(はし)を、ポロッと落とすことも何回かあった。いまでも左の握力はふつうの人以下の30キロぐらいしかない。血行障害によって左右の手の体温が違い、したがって、皮膚感覚も違う。そのため、急にボールを握っても手になじまないのだ。たえずボールを握って、早く自分の皮膚とボールが“いいお友だち”になってくれよ、と囁(ささや)いているのだ。
「日本シリーズというのは独特の雰囲気があるんです。第7戦までやると、同じ対戦相手と一〇日近くゲームをすることになるので、精神的に飽きてくるんやね。ペナントレースは3連戦方式で次々に相手が変わる。これが新鮮な刺激を与えてくれる。いい気分転換になるんです。日本シリーズは同じ相手と6回も7回もつづけて試合をすることになるので、ほんとに疲れるんです」
江夏の中にドテッとトグロを巻く倦怠感に似たものを一掃するための夜遊び、盛大な深夜のお祭りが第7戦の前夜にあったのである。江夏にはそれまで一度も優勝の経験がなく、日本シリーズももちろん初体験である。ペナントレース130試合、そしてシリーズ7試合、実に一年間に137試合もベンチ入りしたことになる。
リリーフ投手の宿命で、登板はいつでもピンチのときと決まっている。最も神経を使う仕事だ。事実、江夏は広島カープ時代、神経性の胃潰瘍(いかいよう)で慶応病院に入院したことがある。いつでも神経をピリピリ尖(とが)らせていなければならないのだ。そんな状況を137試合も経験してきているのだから、精神的な疲労感がどれほど蓄積されているのか、想像もつかない。
第7戦7回裏一死走者1塁で福士投手をリリーフしてマウンドに登ったとき、江夏が真っ先に思ったのは「これで今年の野球は完全に終わりや!」ということだった。
投手人生で最高の一球はインローのカーブ
江夏の長い投手人生の中で、あえて「最高の1球」をあげてほしい、という難題をもちかけると、江夏はしばらく「ウーン」と唸って考えこみ、「やっぱり、“江夏の21球”の中で佐々木恭介に投げたインローのボールになるカーブやろな。あれだけ考えたとおりの組み立て、狙いどおりのコースにいい球がいったんだから、最高やったな」
佐々木はもののみごとに空振りの三振に討ちとられた。「あんなボールをほうれたのはオレしかいない」と江夏は胸を張った。
江夏は正確なコントロールに必要なのは、精神と投球フォームのバランスのよさだと確信している。フォームのバランスは時計の歯車と同じで、一つ狂うとすべての歯車が狂ってくる。どこに手をつけていいかわからなくなる。ひどいスランプに入ったとわかるのは、江夏の場合「足」であった。モーションを起こして膝(ひざ)を上げたとき、すぐに足が地面におりてしまう感じなのだ。膝を残そうと意識すると体全体のバランスが微妙にズレてきて、膝でいいタイミングがとれない。足が自分の意に反して早く下りていくから、球が早く手からはなれてしまう。自信のある投手ほど球ばなれが遅く、それだけ打者はボールを見にくくなり、打ちにくい。自信のない投手ほど早く球をはなしてしまう。これは人間の本能だといっていい。投手に自信がなければ打者は怖い存在になる。怖くなればなるほどボールを早くはなしたい、という気持ちになってしまうのだ。
そういう状態が投手のスランプというものであり、投手の前に、ある日、立ちふさがるように姿をあらわしてくる“巨大な壁”なのだ。
江夏も何度かそんなスランプに襲われ、苦しんだ。そのたびにひたすら練習をし、工夫(くふう)を重ねて、その壁を乗り越えてきた。らせん階段を上る人をはるか真上から見ていると、同じ円周上を永久に歩きつづける円運動に見えるが、真横から眺めるなら、確実に上昇している。スランプを克服して、新しい境地がひらけるとはそういうことなのかもしれない。
江夏が佐々木に投げた第6球目の内角低目のカーブは、まさに精神とフォームのバランスのとれた最高の状態で投げ込んだ、生涯の1球だったのである。
「甲子園はオレのものや」
この1球に次いでもう1球あげるとすれば、阪神時代の最後の年、昭和50年10月1日、甲子園で広島と対戦したときのボールだ。広島は初優勝を目前にしていた。全国は赤ヘルブーム。甲子園も真っ赤な赤ヘルがスタンドを埋めた。この試合は5-3で阪神が勝ったのだが、終盤、二死満塁で相手打者は衣笠というピンチを迎えた。一打同点。この衣笠、広島時代には一番の親友になっているのだから、いささか因縁めいた話になる。衣笠は2-3と粘りに粘った。江夏はこのときはじめて“意識”して、内角胸元へボールになるストレートを渾身の力を込めて投げた。これまた体がねじれるほど渾身の力を込めて振った衣笠のバットは、空を切った。三振。
二死満塁ボールカウント2-3で“意識して”ボールを投げたのは、このあともう一度だけある。昭和57年、日本ハムに移って、これまた西武へ移っていたかつての“女房役”田淵幸一に対して投げたボールだ。このとき田淵は外角高目を狙っているのがすぐに読みとれた。田淵の目がそのように動いている。となれば勝負球は狙った点からボール一個はずれた外角高目のボール球しかない。ストレートは狙いどおりに走り、田淵は計算したように空振りした。三振。見送られたら四球で押し出しという危険な綱渡りであったが、この球なら思わず手を出してくる、と信じて疑わなかった。おそるべき自信であった。
江夏は衣笠を2-3のあとのインハイのボール球で三振に討ちとったあと、記者会見で、「ここは甲子園球場や」とひとことしゃべっている。もうそのころ、江夏の肩はガタガタになって激しく痛んでいた。気力だけで投げ、衣笠をきわどいボールで三振に討ちとった。「甲子園はオレのものや」という江夏の心意気がヒシと伝わってくるではないか。
江夏豊(えなつゆたか)
昭和23年5月15日生まれ。大阪学院高出身。選手実動年数18年。通算投手成績829試合、206勝、158敗、193セーブ。投球回数3196回、被本塁打299本、与四球982、奪三振2987、防御率2.49。個人タイトル:最優秀防御率(44年)、最多勝利(43・48年)、最多奪三振(42・43・44・45・46・47年)、最優秀救援(52・54・55・56・57年)、MVP(54・56年)、ベストナイン(43年)、沢村賞(43年)。
