Sports Graphic Number SpecialBACK NUMBER
<トルネードコラム>
トミー・ラソーダ「“アメリカの父”になろうと思った」
text by

出村義和Yoshikazu Demura
photograph byYukihito Taguchi
posted2015/05/15 06:00
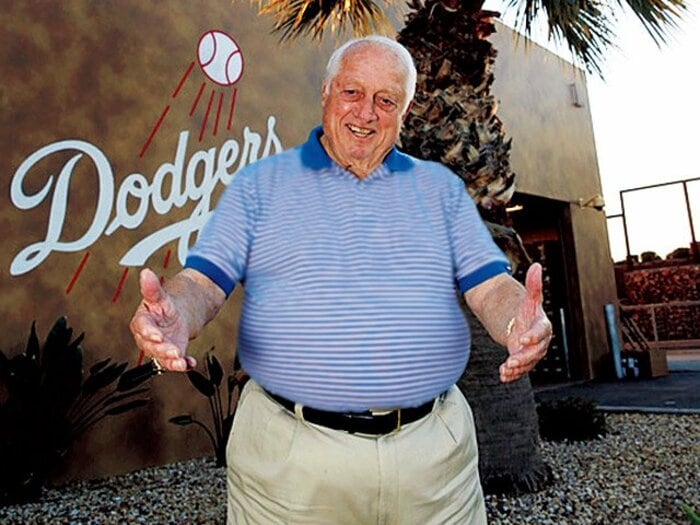
1976年から実に20年にわたりドジャースを指揮した。監督時代の背番号「2」は永久欠番。
「ヒデーオ、ヒデーオ」
野茂英雄を呼ぶ大声が、クラブハウスに響き渡る。声の主はドジャースのトミー・ラソーダ監督だ。
「こうして監督室に呼び入れて試合前の軽食をともにする。トミーのルーティーンのようなものですね」
そう説明してくれたのは、今ではダイヤモンドバックスの球団社長にまで上り詰めた、当時広報アシスタントのデリック・ホール。'95年6月、ドジャー・スタジアムでのことだ。
あれから20年。ラソーダの肩書は球団会長特別アドバイザーに変わったが、87歳になった現在もドジャースの一員、いや顔として、あの頃と変わらぬエネルギーで球団主催のさまざまなイベントでアンバサダー的な役割を果たしている。
こちらは雑誌『Number』の掲載記事です。
NumberWeb有料会員になると続きをお読みいただけます。
残り: 969文字
NumberWeb有料会員(月額330円[税込])は、この記事だけでなく
NumberWeb内のすべての有料記事をお読みいただけます。
