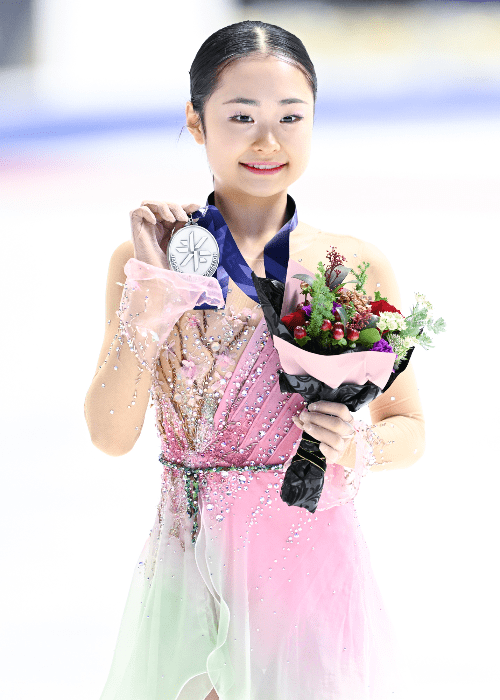鈴木一朗が「イチロー」になった日、仰木彬はこれから起こる何かがわかっているかのように上機嫌だった。
1994年4月7日、神戸市西区のオリックス選手寮「青濤館」に隣接する室内練習場。登録名をカタカナにするふたりの若者、ICHIROとPUNCHの背中を、集めたカメラマンの方へ向けさせると、自分はその間で彼らの肩に手をまわして笑っていた。

チームの広報になったばかりの横田昭作は本来ならば自分がやるべき段取りを全てやってしまった指揮官に呆気にとられるとともに、本当に大丈夫なのだろうか、と心配になった。
「みんなイチローに実力があるとは思っていました。でもまだ高校出て3年目の20歳でしたから、100%活躍するかどうかなんてわからない。本人も『え? 本当にやるんですか?』という感じでしたから。それをああやってバーッと報道陣に向けてやってしまう。今から考えればすごいことですよ」
サングラスの奥で光る仰木の眼が何を見通しているのか、横田にはまだわからなかった。
横田が初めて鈴木一朗を見たのは1992年の晩夏だった。通訳としてオリックス球団に入り、当時二軍の投手コーチだったジム・コルボーンに付いたばかりだった。
『あの51番の選手は絶対に活躍するぞ、絶対にすごい選手になる』
何度聞いただろうか。メジャー通算83勝の右腕は口癖のように言っていた。
確かに見るたびに彼はヒットを打っていた。高卒1年目ながらウエスタン・リーグの首位打者になるほどだった。
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています
この連載の記事を読む
記事