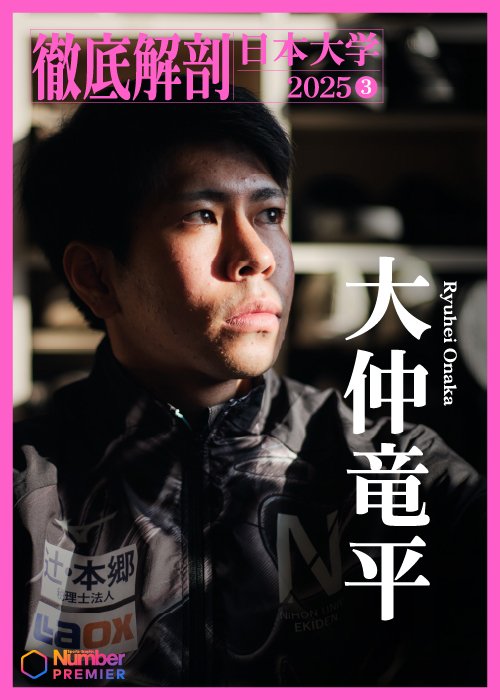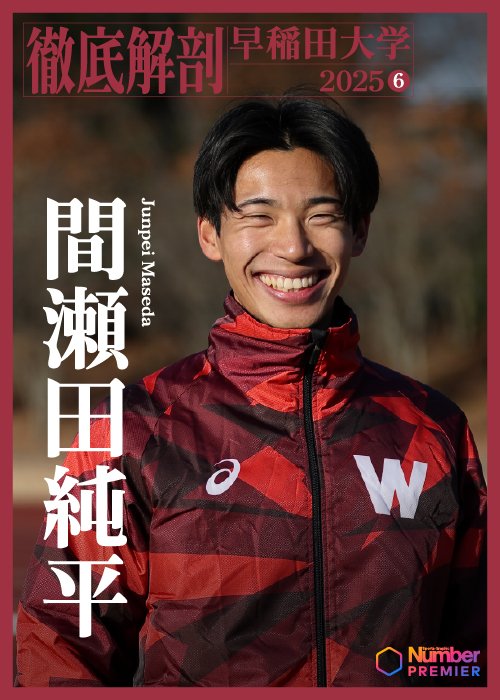マウンドに立った伊良部秀輝は雄弁だった。言葉なしに多くを物語っていた。
《伊良部のやつ、ストレートしか投げたくないって顔をしている》
捕手の青柳進は、1歳下の彼の表情を見て、その胸の内を読み取った。
1993年5月3日、ロッテマリーンズは3点を追う8回裏、とにかく速い球を投げることで知られた6年目の伊良部を登板させた。この回、ライオンズの先頭バッターは4番清原和博であった。ゴールデンウィークの西武球場はこの采配に沸いた。ただ誰よりも高揚していたのは、他ならぬ伊良部本人のようだった。
清原の大きなシルエットが打席に入った。青柳は150kmを超える暴れダマを受け止める心構えをして、ストレートのサインを出した。力と力、決闘の幕が開いた。
3球目、これでもかという形相で放たれた伊良部の剛球に、清原の高速スイングがわずかに重なった。青柳の目の前で一瞬、火花が爆ぜるような音がして、白球はバックネットに衝突した。マスク越しに焦げた匂いがした。息を呑むスタジアム。
清原が打席を外して、青柳を見た。
「きょう、速えな……」
見たことのないものに遭遇したような顔をしていた。
自分は今、とてつもない場面に居合わせている
青柳は痛快な思いだった。1990年代に入ってもパ・リーグは西武の時代であり、清原はその象徴だった。だが、いつも弱者の目線で見上げなければならない常勝軍団の主砲に対し、この日ばかりは対等に構えられるような気がした。それほど伊良部のストレートは速かった。
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています