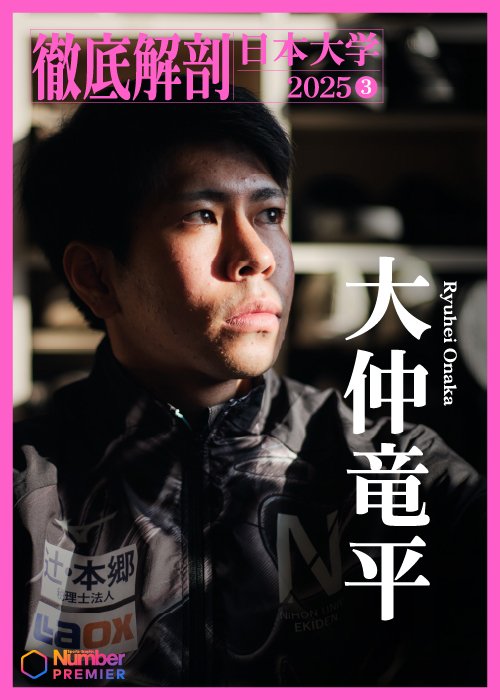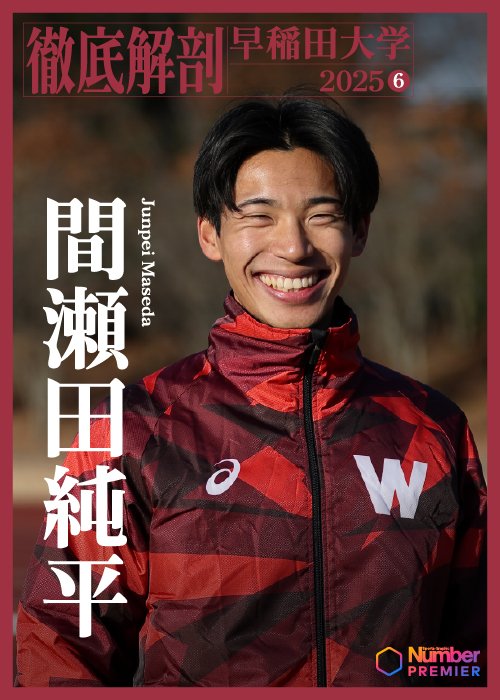現代・大阪の夜を車が走り抜けていく。49歳の辰吉丈一郎は今日も自分の名がプリントされたジャージに身を包んでいる。日々、陽が落ちる時刻になるとジムへ向かう。この日は守口の自宅から南へ40分。堺東のミツキボクシングジム。
幹線道路に面したガラス張りの扉を開けると馴染みの顔が待っていた。
春木博志、51歳。このジムの創設者であり、現在はプロモーターを務めている。
「おう、来たか」「早い時間にすまんね」
話もそこそこに辰吉はバンデージを巻き始める。言葉はいらない。それだけの時間を共有してきた証拠だ。とりわけ二人はボクシング史に残るKO劇をともに闘った。
「僕、そんなにKOは多くないよ。僕より多いボクサー大勢いるんちゃうかな」
辰吉の言葉通り、プロキャリア28戦のうちKO勝ちは半分の14。世界タイトルマッチ11戦に限れば2つ。KO率18%。
では、なぜ辰吉のKOはこれほど脳裏に刻まれ、心に残っているのだろうか。
「考えが古いせいか、僕の中ではボクシングというより拳闘なんです。二つの拳だけで闘う。真剣を持って向かい合って一撃かわされたら殺られる。そういう感覚はありますよ。倒さんことにはやられるという」
かつて辰吉が春木とともに闘ったのも、まさにそんな試合だった。
相手の候補から、迷いなく選んだ。
1997年11月22日、WBC世界バンタム級タイトルマッチ。20歳の王者シリモンコン・ナコントンパークビューに挑戦する27歳、辰吉の勝利を予想した者は少なかった。16戦無敗、3連続防衛中のムエタイ出身王者の強さが知れ渡っていたことに加え、辰吉が世界挑戦3連敗中だったことが悲観論を呼んだ。つまり浪速のジョーの時代はもう終わったという諦観だった。
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています