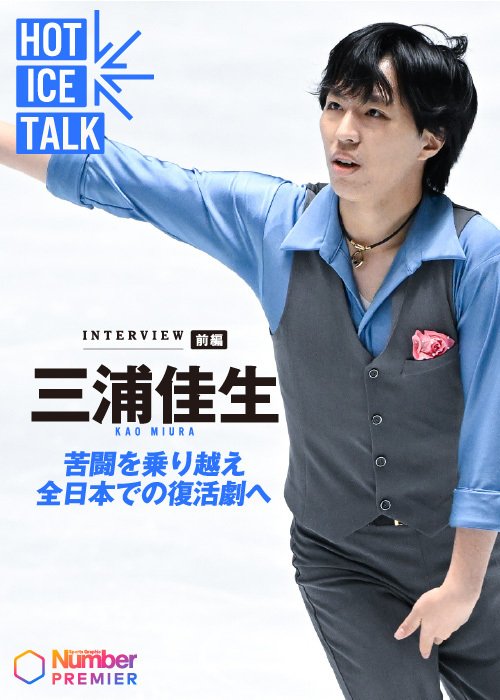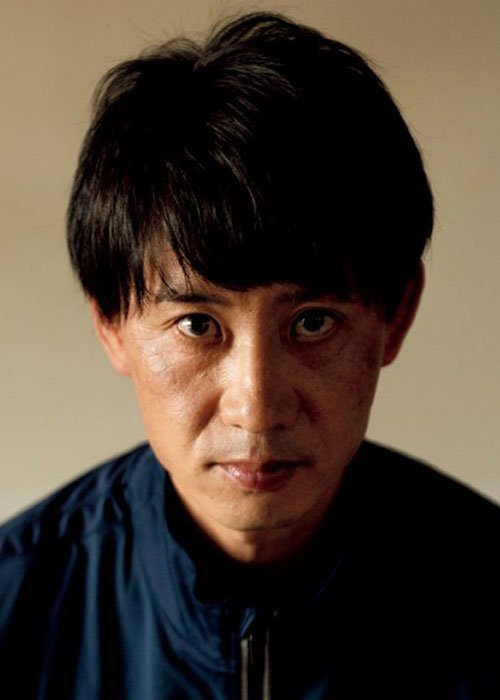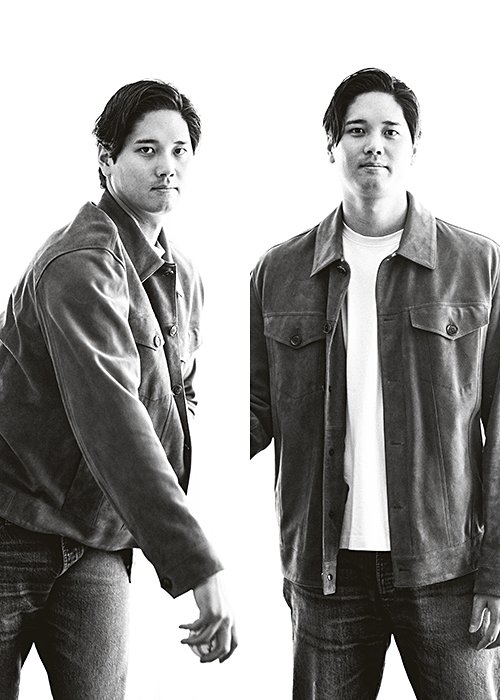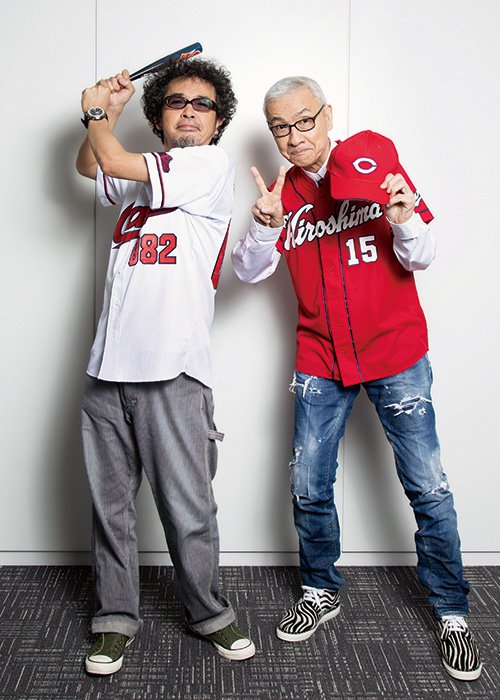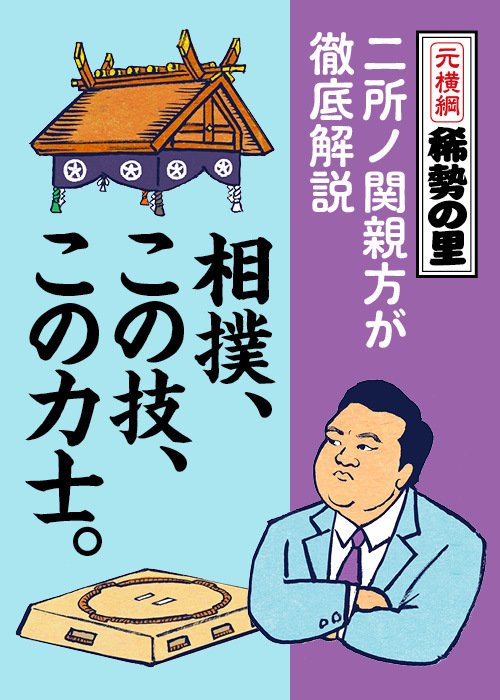――まずは牡馬と牝馬の違いについて伺います。ジョッキーとして、乗り味に違いはあるものですか?
「古い話になりますが、デビュー前のファインモーション('99年生まれ、父デインヒル、母ココット、栗東・伊藤雄二厩舎)にまたがったときに、その力強さに思わず鼻息を荒くしてしまい、伊藤調教師('07年に勇退)に『先生、これでダービーに行きましょう』って言っちゃったことがあります。先生は少しあきれたような顔をされて、素っ気なく『牝馬だけどな』という返事。慌てて馬から下りて、ファインモーションのまたぐらを覗き込んでしまったことを思い出します。牡馬だからこう、牝馬はこうとか、乗った感じだけでわかるものではないとボクは思っています。牝馬らしいな、はもちろんありますよ。新馬戦の返し馬などで周囲の様子を窺う用心深さを見せるのは牝馬が多いですからね。初めての場所、初めての経験でも割と平気でいられるのが牡馬なんですが、気の小ささを指摘されてしまう牡馬も一定数存在するのは皆さんもご承知の通りです」
――牝馬に騎乗するときに、特に気をつけていることはありますか?
「イメージ的にはソフトなタッチを心がけるとかはありますが、古馬になってからは牝だからと明らかに差をつけることはないかなあ。ただ、牝馬は何かのきっかけでレースが嫌になってしまうことがよくあります。急に走らなくなるのは牝馬が多いですよ。レースを嫌なものにしないように気をつけなければいけないんですが、ソフトにソフトにやってたらレースは勝てないですからね。その辺のバランスは難しいところです。調教の現場でも、明確な答えはまだないと思うんですよね。牝馬だからこうしなきゃいけないとか、男馬だとどうだとか。みんなが答えを探しながらやって、走る馬が出たり、出なかったりなんですよね。ボク自身も牝馬との向き合い方がしっかりわかったわけじゃない。古馬のゴリゴリの男馬よりはソフトな仕上げの方がいいのかもぐらいはあるけど、あんまり甘やかしてもな、とも思うわけです。牝馬の追い切りに関しては、男馬と比較してちょっと余裕を残したほうが、というのがトレセン内での共通の認識でしょうか」
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています