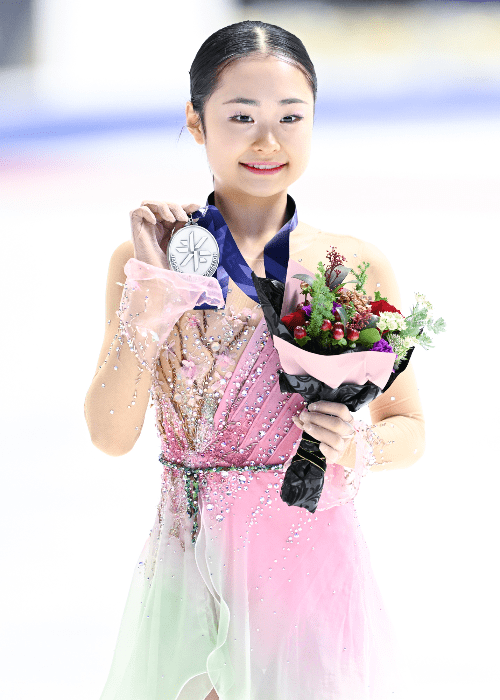自らの意志でジャンプを始める決断を下す。あれから30余年。
2度の所属チームの消滅、家族を襲った不幸。
幾多の困難を葛西紀明はいかにして乗り越えたのか。
関係者の証言で浮かび上がったのは、ある人との強い絆だった。
姉の紀子は、弟がジャンプを始める決意をしたときのことをはっきりと記憶している。
「息子さんには才能がある。今からジャンプをやらせたほうがいい」
弟が小学3年生の冬、自宅を訪ねてきた地元・北海道下川町のジャンプ少年団の関係者2人が、両親と弟を前にそんな話をきりだした。当時、一家が暮らしていた町営住宅はスキー場の近くにあり、窓からはアルペンスキー用のゲレンデと、隣接しているジャンプ台が見えた。弟が遊んでいるときに一番小さな8mのジャンプ台を飛んだことは聞いていたが、指導者に目をつけられるほどの才能があるとは思っていなかった。
「うちはお金がないから、ジャンプをやらせるわけには……」
そう言ったのは、母の幸子だった。父が体調を崩して仕事に就けなかったため、一家の生活がその日の食事に窮するほど苦しいことは、翌春から中学生になる紀子も理解していた。町内で評判になるほど足が速かった弟がそれまで熱中していたマラソンに比べ、ジャンプには遠征費や高価な用具が必要なこと、歯切れの悪い言葉しか返せなかった母が、それ以上の心痛を感じていることもなんとなく想像できた。
「マラソンか、ジャンプか、どっちをやりたいの?」
 ソチのラージヒル2本目を終えて、メダルを確定させた葛西を労う竹内択(右)と清水礼留飛。
ソチのラージヒル2本目を終えて、メダルを確定させた葛西を労う竹内択(右)と清水礼留飛。
幼いころから病弱だった弟が扁桃腺をはらして熱を出すたび、母は弟を自転車に乗せて病院まで走った。弟も母にべったりで、小学1年のときの授業参観で母を見つけると、一人だけ「おかあさーん」と席を立って母のもとへ駆け寄って甘えた。すぐに顔を真っ赤にして席に戻ったのだが、その場面を母は「あのときの紀明の顔、すごかったよ」と嬉しそうに何度も繰り返して話した。
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています