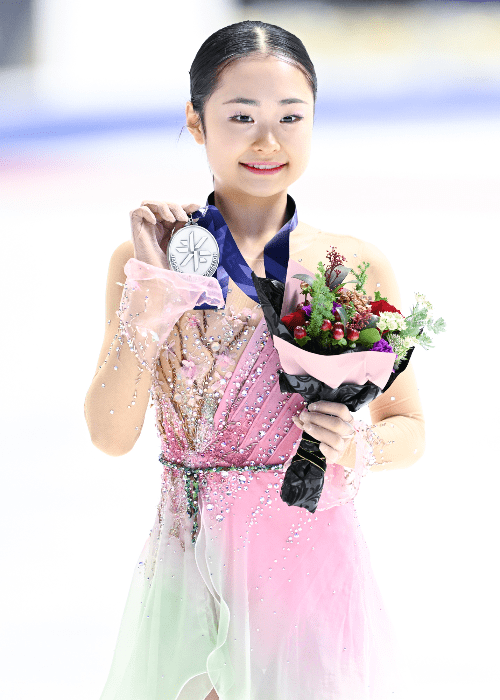行方尚史は夢を描いていた。
まだ19歳だった。
1993年9月29日、小田急線柿生駅のプラットホームに佇み、明後日から始まる日々のことを考えていた。
10月1日付で四段になる。昇段当日からデビュー戦に臨む。本当の勝負の世界を棋士として走り始めるのだ。
手にしていたのは、当日リリースされた小沢健二のファーストアルバムだった。封を開け、歌詞カードに記されたセルフライナーノーツを読む。
「フリッパーズ・ギター」を解散して独りで歩き始めた25歳の音楽家は、芸術と表現に対する決意を表明していた。戦いを始める青年の心に迫り来る何かがあった。
「ああ、すごいなって、胸を打たれたんです。あの頃の僕にとってのスーパースターは羽生さんと小沢健二でした。今までとは違う彼の世界を知ることは僕の原動力になった。あれから1年、あのアルバムを聴きながら挑決まで駆け上がることができたんだから」
青春を盤上に賭ける若者が棋界最高位へと疾走することが時々ある。
季節は決まって夏である。竜王戦決勝トーナメントは熱帯夜の時期を通り過ぎる連戦で争われる。
'87年、飛車が成った盤上最強の駒の名を冠する最高棋戦として創設されて以来、語られ続けてきた「竜王戦ドリーム」には、3つの正体がある。
ひとつは、誰でも叶える可能性のある夢であること。積み上げたものなど関係ない。新四段どころか棋士でなくてもいい。女流棋士やアマチュアも参加する。制度上の極論を言えば、世界中の誰でも竜王になることはできる。
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています