メディアウオッチングBACK NUMBER
レスリングはいかにして
日本の“お家芸”となったのか。
~『日本レスリングの物語』を読む~
text by

大矢博子Hiroko Oya
photograph bySports Graphic Number
posted2012/08/24 06:00
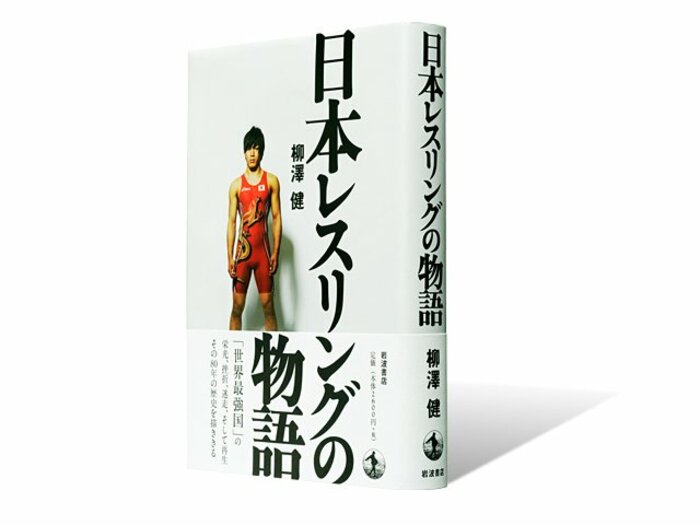
『日本レスリングの物語』 柳澤健著 岩波書店 2600円+税
ロンドンオリンピックが終わった。
予想を超えるメダルラッシュに日本中が沸いた一方で、期待されていた種目で金メダルがとれず、国際舞台で勝ち続ける難しさをあらためて思い知らされた大会でもあった。
そんな中、戦後日本がオリンピックに復帰した1952年ヘルシンキ大会以降一度も欠かさず、参加したすべての大会でメダルを取り続けているのが、レスリングだ。レスリングはもはや日本のお家芸のような気持ちですらいた――のだが。
ADVERTISEMENT
日本レスリング黎明期から現代までの歴史を綴った柳澤健『日本レスリングの物語』は、そんな表面的な思い込みを跡形もなくぶっ飛ばしてくれた。
1921年3月に靖国神社で行なわれたプロレスラーのアド・サンテルと早稲田大学柔道部の庄司彦雄による異種格闘技戦が日本レスリングの始まりだそうだ。
庄司はその後アメリカに留学、プロレスも学び、帰国後は早稲田大学にレスリング部を創設。このとき早大レスリング部の初代主将だった講道館四段の八田一朗が、本書の主役のひとりである。
この八田一朗が、とにかくすごい。
レスリング強化のためブレない姿勢を貫いた、八田一朗という男。
黎明期の日本レスリングは柔道との関係を抜きには語れないが、当時の柔道界はレスリングを見下していた。両肩がマットについたら負けなのに、講道館はアムステルダム五輪に巴投げの名手を出したのだから無理解のほどがわかる。
柔道とレスリングの違い、日本と海外の実力の違いを知っていた八田は「日本のレスリングの未来をはっきりと見通しているのは自分ひとり」という思いでなりふりかまわず、レスリングの普及と強化のためにかけまわることになる。
柔道界との確執だけではない。戦争による停滞。派閥争い。妨害工作。国際試合を主催しても共産圏の選手にビザがおりず、外務省に掛け合う。ひとつのスポーツが定着するまでにはこれほど「マット外」の戦いがあるのかと呆然とした。外国人コーチを招聘したり、派手なパフォーマンスでメディアを呼び込んだりという今ではごく普通の戦略も、八田が最初にやったことなのだそうだ。
敵も多かったが、レスリング強化のためという一念からまったくブレないこの姿勢が、今の隆盛を作ったことは間違いない。彼のパワーが本書のページからほとばしり、読者を圧倒する。
