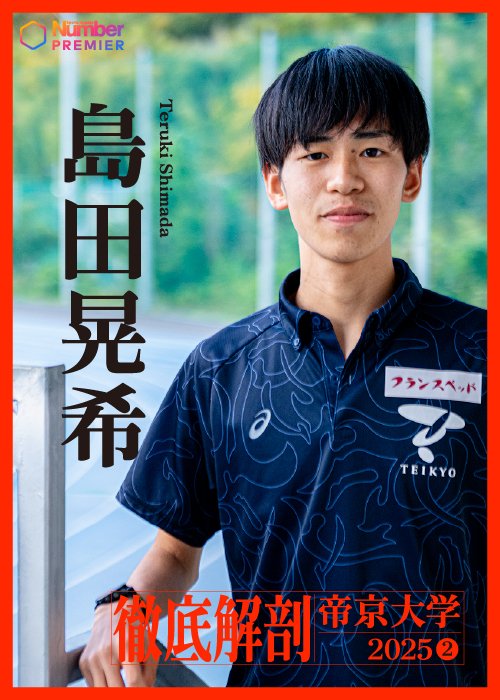記事を
ブックマークする
「捕手は『疑い屋』であるべき」梅野隆太郎&坂本誠志郎が『野村ノート』から学んだこと「結局、人としてどうあるべきか」【阪神タイガース】

東京某所の高級料理店。重厚な扉を開いた瞬間、梅野隆太郎は全身を硬直させた。目の前に野球界の重鎮、野村克也が深く腰掛けていたのだ。慌てて隣に視線を向けても、西岡剛はほくそ笑むばかり。プロ4年目の2017年春、まだ阪神正捕手の座を奪えていなかった25歳当時の記憶だ。
「完全にサプライズでした。チームが勝つためにコイツをなんとかしようと、西岡さんが考えてくれたのかもしれません」
伏線はあった。7歳上の先輩から食事に誘われた際、妙な注文を受けていた。「ペンとノートを持ってこい」。少なからず違和感は覚えていたが、まさか……。
大卒1年目から3年間の出場試合数は92、56、37。殻を破れずにいるのは自覚していた。1時間30分のぜいたく過ぎる即席講座。迎えの車に乗り込んだ野村に頭を下げた時、両手は冷や汗でベタついていた。
「聞き逃さないように必死で、目線を落とす暇もないぐらいで。その場ではポイントだけ箇条書きして、ホテルに戻ってから一気に清書しました。野球人である前に、人としてどうあるべきか。『野村ノート』に書かれていた内容を思い出しました」
梅野「プロは配球の細かさが天と地ぐらい違った」
阪神入団直後、レジェンドの著書『野村ノート』を開いた。当時のヘッドコーチは黒田正宏、一軍バッテリーコーチは山田勝彦。前者は南海と阪神、後者は阪神と楽天で野村イズムをたたき込まれている。名著との出会いはある意味、必然だった。
ルーキー捕手はその頃、苦悩していた。
「学生時代と比べて、プロは配球の細かさが天と地ぐらい衝撃的に違ったんです。特にインサイドの使い方、ですね。プロで初めて外国人選手と対戦して、外角の“手伸びゾーン”の怖さを知った。それでベース板をもっと広く使わないと、となって」

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています
この連載の記事を読む
記事