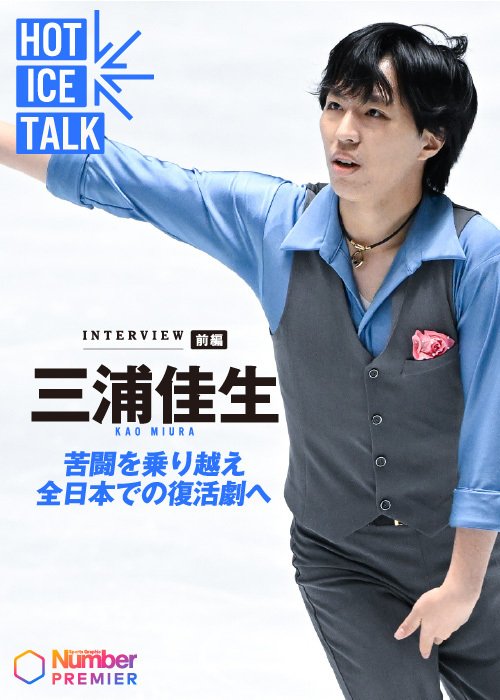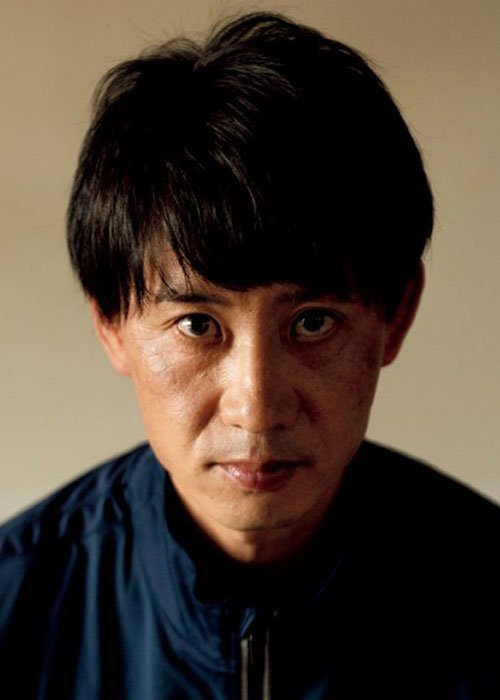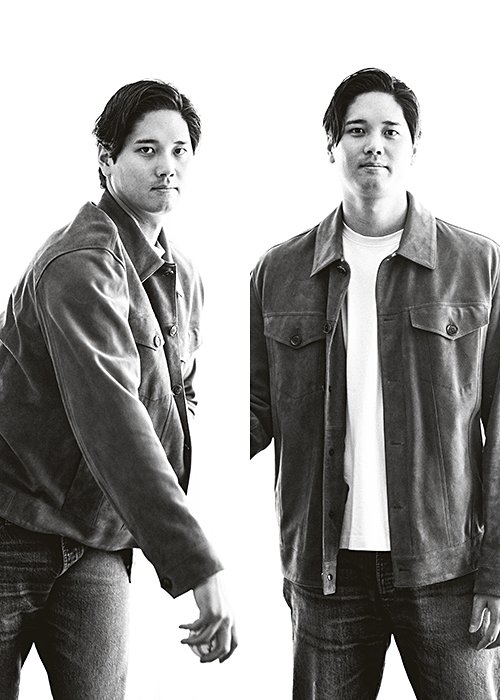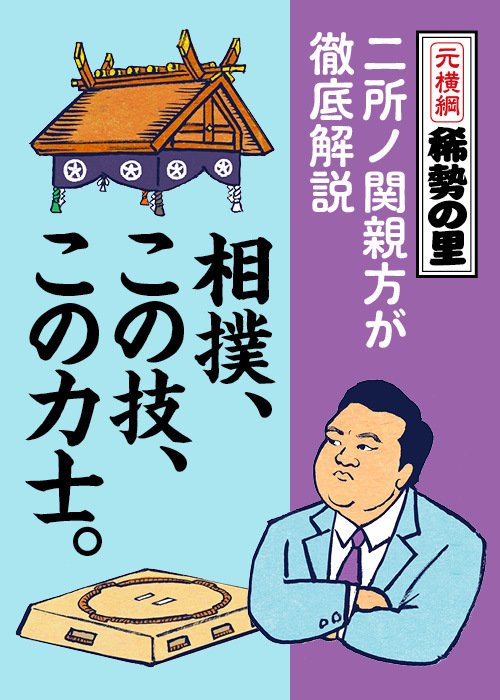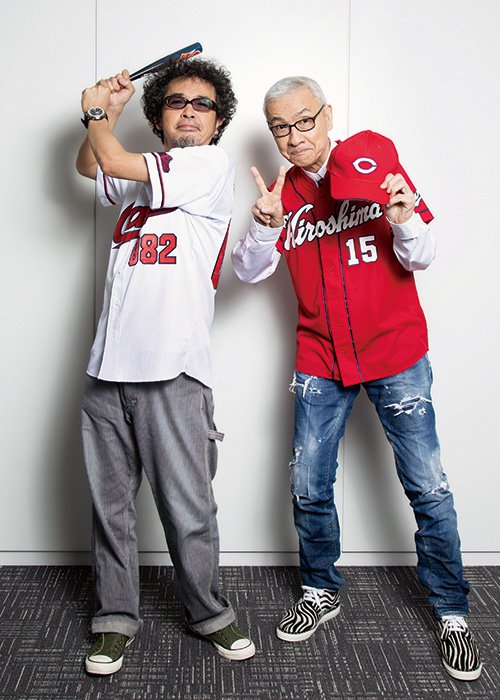記事を
ブックマークする
「閉鎖的なF1村の文化と慣習を一変させた」レッドブルの速さだけではない“戦略”を読み解く「予算管理は実に厳格で、日常的な評価や査定も…」

「角田裕毅、レーシングブルズからレッドブルのドライバーに昇格」
時ならぬ一報に、日本中が沸き立ったのは無理もない。レッドブルは2010年頃からF1の強豪チームに成長。2度の黄金時代を築いただけでなく、F1が今日のようなホットなエンターテインメントに変貌する、トレンドセッターの役割も果たしてきた。そんなチームに日本人ドライバーが名を連ねるのは、まさに快挙だった。
ならばレッドブルは、なぜかくもスペシャルな存在になったのか。まず挙げられるのは潤沢な資金力とユニークな発想、アイデアをすぐに実践する行動力だ。
レッドブルF1チームは'04年、ジャガーチームの買収で誕生したが、当初は真意を測りかねると指摘する声もあった。
むろん参戦の目的は、自社製品のブランディングとマーケティングにある。同社はエクストリーム系からサッカーにいたるまで、ありとあらゆるスポーツでスポンサーシップを展開。「挑戦」「アドレナリン」「ライフスタイル」といったキーワードを絡めながら、年間販売本数126億7000万本、売上約1兆7900億円(2024年度)を誇るエナジードリンクを世界中でPRしてきた。しかし精力的、かつ多岐にわたる支援活動の故に、F1の活動も資金力を背景にした販促施策の一環に過ぎないのではないかと受け止められたのである。
極めて異例な2チーム運用を開始
ところが彼らは本気だった。参戦初年度の'05年、コンストラクターズランキングを7位で終えたレッドブルは、チームの技術的な基盤を強化するために、デザイナーのエイドリアン・ニューウェイをマクラーレンから招聘。若手のドライバーに経験を積ませるべく、ミナルディも買収して「スクーデリア・トロロッソ(現・レーシングブルズ)」と名付け、極めて異例な2チーム運用を開始した。
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています
この連載の記事を読む
記事