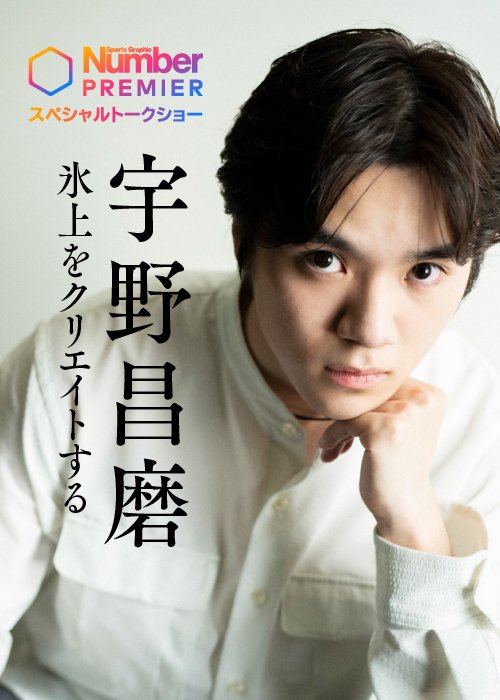日本初の国際競走として1981年に創設されたジャパンCは、'90年代に入るあたりから成熟期を迎えた。黎明期とは打って変わって、海外のトップホースが続々と参戦してくるようになったのだ。
外国馬の陣容が年々、分厚くなっていった背景にはいくつかの要因があった。回数を重ねながら着実に高まってきたレースの知名度。当時は世界屈指といえた高額賞金。迎え撃つ日本馬がまだ、外国馬を圧倒する存在ではなかったことも理由のひとつだ。相手は与しやすく、賞金は高い。まして渡航費用は主催者持ちの招待競走があると知れば、誰だって出掛けてみたくなる。
「レース史上でも最強の布陣」との外国馬評は、ニュージーランドのホーリックスと稀代のアイドル・オグリキャップがクビ差の激闘を演じた'89年から目立ち始め、次の年(優勝馬は豪州のベタールースンアップ)も使い回された。翌'91年の外国馬こそ「ここ数年に比べると数段落ちる」という触れ込みだったが、日本の総大将メジロマックイーン(4着)をズドンと差し切った米国のゴールデンフェザントは、日本でも名高いアーリントンミリオン(世界初の賞金総額100万ドル競走として'81年に創設)の勝ち馬。2着のマジックナイト(仏)は同年の凱旋門賞2着馬である。
「ジャパンCもついに、このレベルの大物が本気で狙ってくるレースになったのかと思うとオレは感慨深いよ」
第1回のレースから取材してきた私の上司が、しみじみとそう漏らしていたことを覚えている。
全ての写真を見る -1枚-プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています
この連載の記事を読む
記事