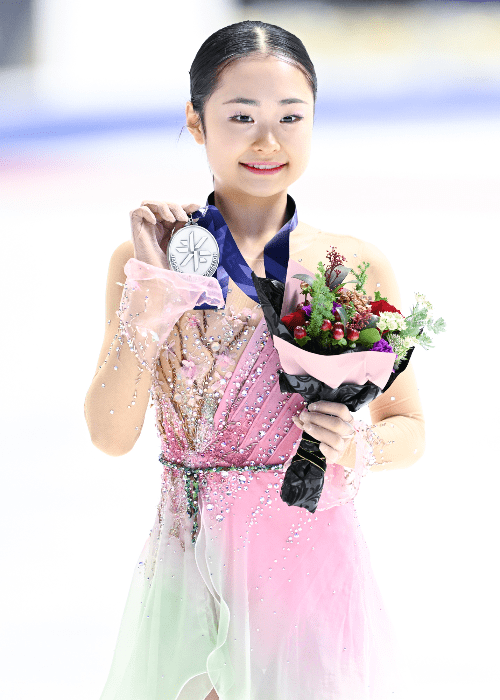選手権において初めて国立競技場のピッチに立ち、初ゴールまで決めた1年時の鹿児島実業戦でもなければ、自らの2ゴールでチームに栄冠をもたらした3年時の筑陽学園戦でもなかった。
平山相太が選手権における最も印象的なゲームとして挙げたのは、自身の無力を突きつけられた一戦だった。
「市船戦ですね。2年のときの決勝の。あれが選手権で負けた唯一の試合なので」
1学年上の大久保裕樹、小宮山尊信、青木良太、さらに同学年でライバルと認める増嶋竜也――のちに全員がJリーガーとなる市立船橋の守備陣を前に、大会得点王の2年生エースは沈黙し、国見は戦後初となる3連覇の夢を絶たれた。
「ディフェンスの4枚はみんな競り合いに強かったし、中盤のプレスバックも凄くて。自分は何もさせてもらえなかった」
優勝するのが当たり前――。
そんな常勝軍団に身を置くと、喜びよりも悔しさのほうが深く刻まれるのかもしれない。一方で、自身の不出来を鮮明に覚えている点に、平山の性格も表れている。
高校サッカー界の中心・国見。
もっとも、忘れ得ぬ記憶は、ロッカールームの光景とセットになっている。
泣きじゃくる3年生を横目に、総監督の小嶺忠敏とコーチが何やら話し込んでいた。
「長崎までマイクロバスで帰るんですけど、その途中で1、2年生は練習試合を転戦するんです。そのチーム分けをしていた。もう次の戦いに目を向けていて、勝負への情熱が凄いなって(笑)」
2000年代前半、高校サッカー界は長崎の国見を中心に回っていた。
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています