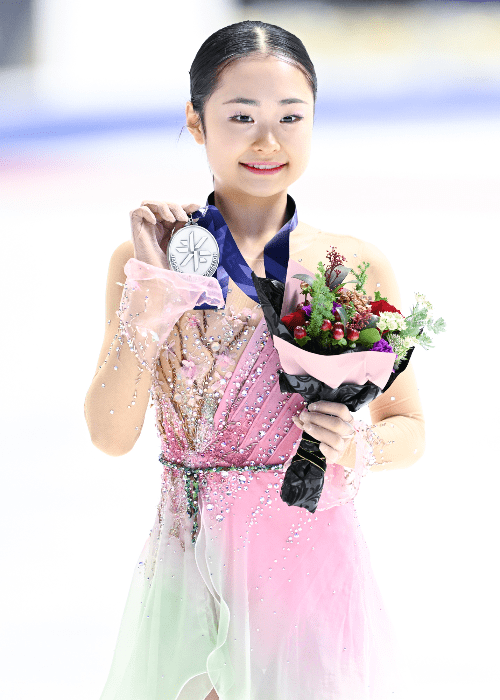悔しくて、悔しくて、試合終了後の記憶がほとんどない。
とにかく泣いた。嗚咽が止まらなかった。2時間、いや、それくらい長く感じただけで、実際のところは30分もすれば涙も乾き、呼吸を整え、平静を取り戻していたかもしれない。わからない。
きっとそんなヤツが何人もいたに違いないロッカールームで、3年間ずっと厳しかった古沼貞雄先生は何を話したのだろう。記憶にない。覚えているのは、帰りのバスが渋滞に巻き込まれたことだけだ。何だよ。いつになったら着くんだよ。マジで。雪のせいでめちゃくちゃな一日だ――。
あれから22年もの歳月が過ぎたなんて信じられないほど、時の流れは早い。
すでに現役引退を発表していた木島良輔にとって、2019年12月14日はプロ選手として過ごす最後の一日だった。いつの間にか40歳という「ウソみたいな年齢」になったが、表情や態度から伝わってくるヤンチャでシャイなキャラクターは帝京の10番を背負ったあの日と変わらない。

「渋滞を抜けて、学校か寮に帰って……。俺の中にあるその次の記憶は、キャンプですからね(笑)。横浜マリノスの一員になって初めてのキャンプ。それからずっと、必死でプロの世界にしがみついてきただけだから、あの雪の決勝について振り返る機会なんてなかったんですよ。当時の仲間と酒を呑む機会があっても、バカな思い出話しかしないでしょ? もったいないよね。うん。いい機会だから、今日、ちゃんと振り返ります」
プラン紹介

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています