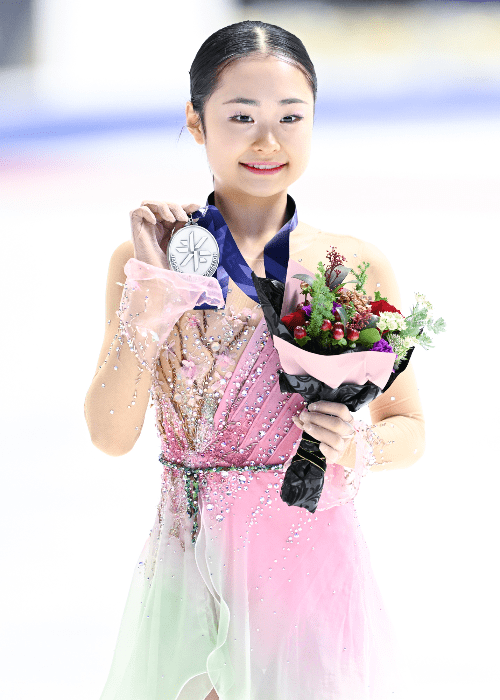2019年、大船渡の町は剛球投手の出現に沸いた。高校生史上最速、163kmの直球を携え、35年ぶりの甲子園へ。風は確かに吹いていた。その姿を見つめる、かつてを知る人々の瞼に浮かぶのは、あの春のセンバツを一人で投げ抜き、ベスト4へと導いた小柄な左腕の残像だった――。(Number984号掲載)
エースは虚空を見ていた。視線が向けられているのは眼前の戦いか、どこか先の未来か、判別がつかない。最後の攻撃。仲間たちが立ち上がって声をあげる中、ベンチに座ったままじっと何かを考え込んでいるような、そんな眼差しだった。
甲子園をかけた決勝戦、佐々木朗希は一度もグラウンドに立たなかった。
「故障を防ぐために投げさせませんでした。連投で、暑い。壊れるか、壊れないかというのは未来なので知ることはできないですけど、勝てば甲子園という素晴らしい舞台が待っているのはわかっていたんですけど、決勝という重圧のかかる場面で、3年間の中で一番壊れる可能性が高いと思いました。投げなさいといえば、投げたと思います。ただ、私にはその決断はできませんでした」
プラン紹介

特製トートバッグ付き!
「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています

特製トートバッグ付き!
「雑誌+年額プラン」にご加入いただくと、全員にNumber特製トートバッグをプレゼント。
※送付はお申し込み翌月の中旬を予定しています
photograph by Katsuro Okazawa