Number ExBACK NUMBER
名作ノンフィクション 「江夏の21球」はこうして生まれた 【連載第2回】
text by

岡崎満義Mitsuyoshi Okazaki
posted2009/04/02 10:00
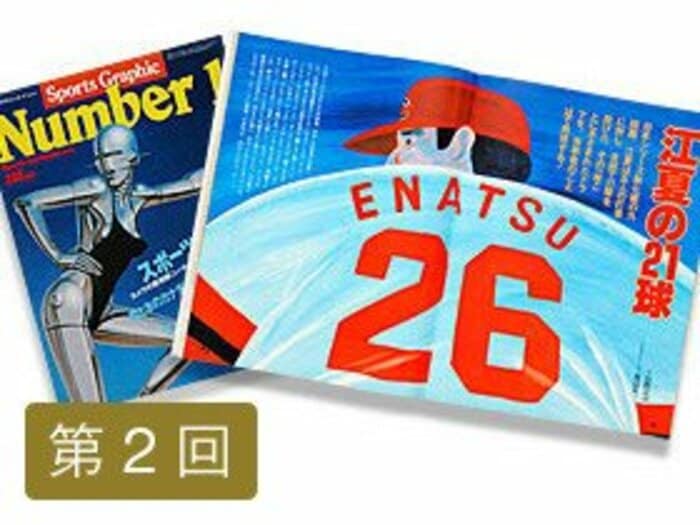
「お前が辞めるなら、オレもユニフォームを脱ぐ」
佐々木への第4球を投げる前に、テレビの画面は、1塁手の衣笠祥雄がマウンド上の江夏のそばにやってきて、何ごとかひとことふたこと、話しかけるシーンになった。
「江夏さん、衣笠はこのとき何をしゃべったんですか」
ADVERTISEMENT
と、ぼくは江夏にたずねた。ところが、それまで機嫌よく、まことに明快に自分の一球一球を解説してくれていた江夏が、急に表情をこわばらせて、
「それは話すわけにはいかんな」
と、言ったのである。意外であった。
「どうしてですか」
「いや、これにはちょっとわけがあるからな、まだ話せんのや」
「そんなこと言わずに、教えて下さいよ」
「いや、やっぱり駄目や」
そんなちょっとした押し問答があった。仕方なくそのシーンはそのままにして、とにかく最後までビデオを見ることにした。そのあともこの場面以外は江夏はまた明快に話してくれた。少し休んだあと、もう一度ビデオテープを巻きもどしてあらためて最初から見ることにした。聞き落としたことなどを質問し、江夏の言いたりない点を補充するためである。
二度目に問題のシーンにぶつかって、しぶる江夏をとうとう口説き落とした。
江夏はそのとき、頭にカッと血が上っていたのである。藤瀬が3塁、アーノルドの代走・吹石が二盗をきめたとき、広島のベンチから3塁のブルペンに池谷公二郎と北別府学が走り、投球練習を開始したのである。江夏はそれを見て、自分の目を疑ったほどであった。
この土壇場(どたんば)にきて何でリリーフ投手を準備するのだ。オレこそ、今年一年130試合すべてにベンチ入りして、監督の声がかかればいつでも飛びだしたリリーフ・エースではないか。オレ以上のリリーフがいるわけがない。絶体絶命のピンチは腹をすえてリリーフ・エースのオレにまかせていいではないか。なのに、ブルペンで二人がピッチングをはじめている。結局オレは監督から完全な信頼を得ていなかったのか。何のために130試合ベンチ入りしてきたのか。
「マウンドにグローブを叩きつけてベンチに帰りたい気持ちやった」と、江夏は言った。
江夏と衣笠はチームの中でいちばん気の合うチームメイトであった。衣笠には、江夏のやり場のない怒りが、いまにも爆発しそうな風船のように、ふくらんでいくのがわかった。自尊心を傷つけられた江夏は、放っておけばマウンド放棄も辞さないように見えたのである。それどころか、ユニフォームを脱ぐかもしれないと思われた。こいつはヤバイ!
気配を察した衣笠はマウンドに歩み寄って、いきなりこうささやいた。
「おまえがユニフォームを脱ぐなら、オレも辞めるぞ」
そのひとことを聞いて江夏は、
「ああ、オレの気持ちをちゃんとわかってくれてるヤツがいる!」
そう思ったとたん、それまで怒りで爆発しそうになっていた気持ちが、スーッとおさまり、集中力を回復したという。古葉監督に対する不信感と、衣笠に対する感謝の気持ちを、マウンド上の江夏はほんの数十秒の間に味わったことになる。これが問題の江夏―衣笠の立ち話シーンであった。
近鉄のバッターよ、おまえらも全力でぶつかってこい!
古葉監督がそのとき考えていたのは、同点で延長戦に入ったときのことである。日本シリーズでは午後五時半をまわって新しいイニングに入らないという規定がある。そのとき時計の針は四時半をさしていた。まだ時間は十分にある。もし延長戦に入れば、江夏に代打を出すケースもありうる。とすれば、江夏をリリーフする投手の準備をしなくてはならない。古葉監督は当然やるべきこととして、池谷と北別府に投球練習を命じたのである。
江夏の気持ちはまるで違っていた。江夏にとってこの試合、この9回裏が今シーズンをしめくくる最後の場面なのであった。勝つか負けるかのどちらかしかないと意識されていた。引き分けとか延長とかということは考えもしなかった。これが130試合のペナントレースの1試合だったら、江夏の感情もこれほどまでにたかぶることはなかったであろう。一年のどんづまりのゲーム、という意識が強かった分だけ、古葉監督への不信がつのったのだ。
この9回裏の二人の気持ちのすれちがいが、シーズンオフの江夏放出、日本ハムの高橋直樹投手とのトレードに発展したのではないかとかんぐりたくなるが、その後、江夏と古葉の二人にたしかめてみると、そんなことはないと二人とも強く否定した。
しかし、真っ赤に焼けた鉄を打つとき、まじりこんだ異物がそのまま鉄の中に鋳込(いこ)まれて傷痕(きずあと)を残してしまったのではないか、という気持ちもまだ少しある。そのまた一方で、江夏の野球人生の最高場面といってもいいあの「9回裏」は、まさしく高温高圧の溶鉱炉のようなもので、少々の異物など瞬時に蒸発したとも考えられる。決定的瞬間に起こった出来事だけに、ぼく自身はいまもどちらとも決めかねている。
とにかく江夏は、衣笠の「おまえがユニフォームを脱ぐなら、オレも辞めるぞ」というひとことを耳にして、気持ちが平静になったのである。集中力を回復した江夏は再び打者にたち向かっていく――。
その話を聞いたとき、「できた」と思った。テレビはロングショット、クローズアップをさまざまな角度から自在に使いこなして、球場で見る以上に野球のシーンを面白く、克明に見せてくれるが、それでもなお見えないものがある。それはプレーヤーの心だ。
江夏―衣笠の例でいえば、二人が何か話しているシーンは見ることができるのだが、何を話しているのか、二人の心理がどうなっているのかは、テレビには映らないのである。スタンドで見ていても、もちろんわからない。それを取材の仕方――たとえばビデオという武器を使うことによって発掘できる、という確信をそのとき得たのである。
9回裏の場面をつづける。
衣笠のひとことで心がスーッとした、という江夏はこんなことを考えた。
「それにしても無死満塁。どう考えてもこっちが不利。たぶん、逆転負けになるだろう。しかし、同じ負けるにしても、四球の押し出し、野手のエラー、ポテン・ヒットなんかで負けたくない。負けるならホームランでもヒットでも火の出るような当りをされて、いさぎよく負けたい。オレはそういう気持ちや。近鉄のバッターよ、おまえらも全力でぶつかってこい! そう思ってあとのバッターに対したんやね」
これがリリーフ・エースの美学である。自尊心というものである。佐々木は結局、3塁線の惜しいファウルのあと、内角高目のカーブをまたファウル、次は内角低目の直球でボール、最後、内角低目のカーブで空振り三振だった。集中力をとり戻した江夏がのりうつったような力のこもったボールだった。これでワンアウト。
次は石渡(いしわた)茂である。まだ一死満塁、近鉄のチャンスは続いている。近鉄の一打サヨナラの場面は依然(いぜん)として続いている。一般的にいえば近鉄有利である。しかしすでに、腹立たしい気持ちが完全にふっきれて無心の状態にある江夏の方が石渡より優位に立っていた。近鉄にほほえみかけていた勝利の女神が江夏と石渡を見くらべ、こんどは広島に顔を向けはじめたのである。
追いつめられて緊張した石渡は第1球の内角高目のカーブを茫然(ぼうぜん)と見送った。ストライク。第2球にスクイズのサインが出た。石渡はそれを確認した。江夏は2球目、カーブを投げるつもりで投球動作に入ったとき、石渡のバットがスーッと動くのを目の端(はし)でとらえた。スクイズだ! いつくるか、いつくるか、と思っていたものが、ついにきたという感じだった。スクイズをはずすには、速い球を外角高目にはずすにかぎる。それが定石(じょうせき)である。しかしこのとき江夏はカーブの握りのまま、投球モーションに入っていた。もはや握りなおすことはできない。そのままの握りで、思い切って外角高目にはずすボールを投げた。石渡が差し出したバットはとまどったように揺れ、空振りにおわった。球はバットの下をくぐり抜けて、水沼捕手のミットに入ったのだから、当てられないような球ではなかった。緊張のあまり、石渡の腕が縮んでいたのだろう。
3塁ベースを勢いよく飛び出した藤瀬は、あえなく3本間で挟殺(きょうさつ)された。一瞬にして2アウト、ランナー1、2塁。石渡のカウントは2-0。江夏は完全に優位にたった。打者の石渡はさらにかたくなり、からだ全体が縮んでいくような気がした。3球目の内角低目の直球を、振りおくれ気味に1塁線ファウル。それがやっとだった。江夏にとって9回裏の21球目は内角低目のカーブだった。石渡のバットは空を切った。三振。ついにゲームセットとなって広島の優勝が決まった。
テレビ中継では描けないドラマ
ある一つのシーンに徹底的にのめりこんでいくには、時間をストップさせなければならない。現実の時間を追いかけていくテレビ中継ではそれはできない。球場に足を運んでも不可能である。当事者が心を開いて語ってくれるときにはじめて可能になる。
スポーツはドラマだとよく言われる。これはスポーツには筋書きがなく、何が起こるかわからないことを言ったことばである。ハプニングの風にうたれる心地よさ、カタルシスと言いかえてもいい。
実は、もう一つのドラマがある、と江夏の21球の取材をとおして感じた。精神、頭脳のドラマ性とでも言ったらいいだろうか。何が起こるかわからない、というドラマでなく、むしろ、どのシーンにドラマを発見し、発掘するか、というそのときの「ドラマ」である。
江夏の9回裏の21球の中にドラマがあるはずだ、とまず直感した。そしてビデオという武器を使って、江夏の心を開き、21球の一球一球にこだわりつづけているうちに思いもよらない江夏―古葉、江夏―衣笠の間に生じた「ある感情」が見えてきたのである。
その「感情」は野球の選手だけに特別に発生するものではなく、広く人間に共通する「感情」である。野球を見ながら、いつのまにか「人間」を見ているのである。そういう共感のドラマを発掘できると確信した。
「江夏の21球」は若いライターの山際淳司さんが上手に書いてくれた(角川書店刊『スローカーブをもう一球』の中に入っている)。山際さんがスポーツ物を書いたのはこれがはじめてであった。このドラマ発掘は山際さんにとっても新鮮な経験となったらしく、以後、次々とスポーツ物を書いていくようになった。
スポーツはなぜ面白いのか。なぜあんなにわれわれの心を熱くするのか、の答えもその「人間」のドラマの中にある。スポーツはヒューマニズムである、と言い切っていいと思う。人間の肉体と精神の動きが読みとりやすい形で露出してくる。それに身を寄せ、心を寄せ、共感するだけでいい。スポーツはクルマや冷蔵庫などの物をつくったりすることはない。実業ではなく虚業である。しかし、それ以上に大切なヒューマニズムを強化するものである。そこが「たかがスポーツ、されどスポーツ」といわれるゆえんである。
江夏豊(えなつゆたか)
昭和23年5月15日生まれ。大阪学院高出身。選手実動年数18年。通算投手成績829試合、206勝、158敗、193セーブ。投球回数3196回、被本塁打299本、与四球982、奪三振2987、防御率2.49。個人タイトル:最優秀防御率(44年)、最多勝利(43・48年)、最多奪三振(42・43・44・45・46・47年)、最優秀救援(52・54・55・56・57年)、MVP(54・56年)、ベストナイン(43年)、沢村賞(43年)。
